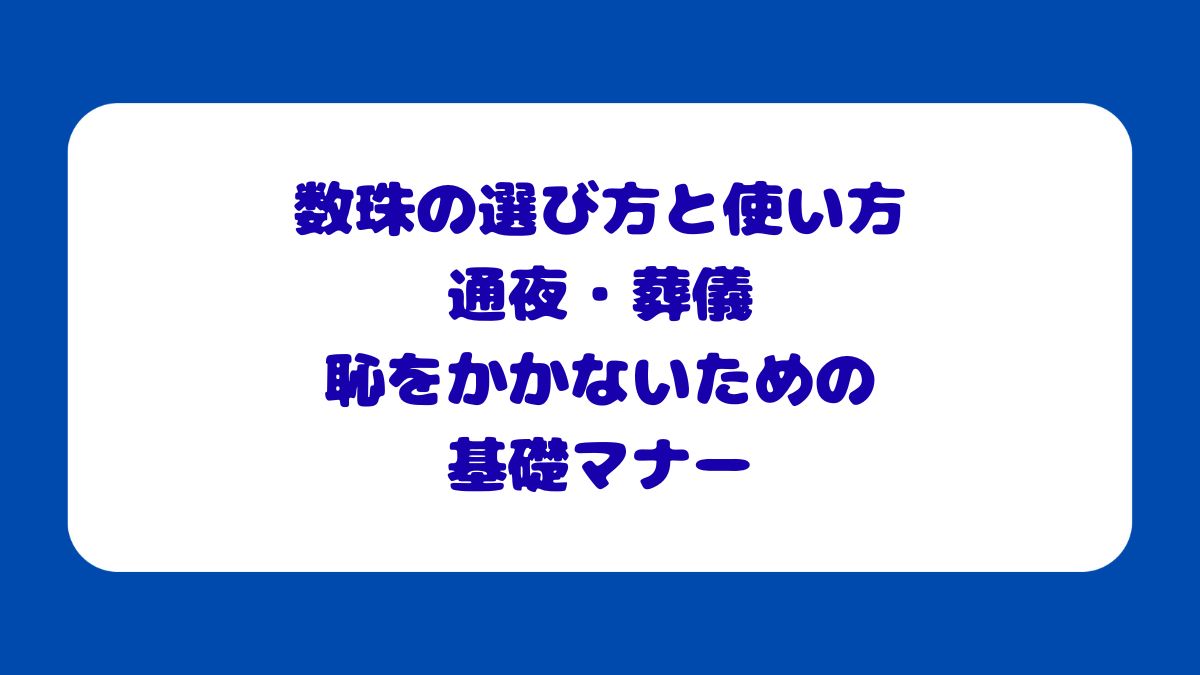通夜や葬儀に参列する際、「数珠(じゅず)は必要なの?」「略式でも失礼じゃない?」「持ち方や使い方に決まりがある?」と悩む人は多いです。
社会人としてのマナーが問われる弔問の場では、正しい数珠の知識があるかどうかが、意外なほど印象を左右します。
この記事では、数珠の意味、選び方、使い方、宗派別の違い、持ち歩きのマナーなど、通夜や葬儀で恥をかかないためのポイントを網羅的に解説します。
数珠とは?仏教における意味と持つ理由
数珠は、仏教の修行や念仏に使われる法具で、珠を繰りながらお経や念仏を唱えるための道具です。
108の煩悩を表す108珠を基本とし、それを略した形が略式数珠です。
葬儀・通夜の場では、故人の冥福を祈る気持ちを形に表すものとして使います。
数珠を持っていないとマナー違反というわけではありませんが、持っていることで仏事に対する敬意が伝わります。
仏式・神式・キリスト教式|数珠の必要性は?
数珠は仏式葬儀では必須に近い持ち物です。
特に年配の参列者が多い葬儀では、数珠がないと「常識がない」と思われることも。
一方で、神道やキリスト教の葬儀では数珠は使いません。
神式では「玉串拝礼」、キリスト教では「黙祷・献花」が中心です。
事前に確認したいポイント
- 訃報の連絡で宗派が明示されているか
- わからない場合は仏式と考えて略式数珠を持参すると安心
男女別|数珠の選び方とおすすめ素材・デザイン
男性用数珠の選び方
男性用数珠はやや大ぶりで、落ち着いた色合いが好まれます。
- 珠のサイズ:10mm〜12mmが一般的
- おすすめ素材:黒檀、紫檀、虎目石、オニキス
- 価格帯の目安:3,000〜20,000円
- 房の種類:一本房・頭付房(控えめな印象)
女性用数珠の選び方
女性用はやや小さめで、色味がやわらかい素材が人気です。
- 珠のサイズ:6mm〜8mm
- おすすめ素材:本水晶、ローズクォーツ、白瑪瑙、藤色ガラス珠
- 価格帯の目安:2,000〜15,000円
- 房の種類:梵天房、切房(装飾性あり)
子供・学生の場合は?
未成年の場合、数珠の携帯は必須ではありませんが、持っていると丁寧な印象を与えます。
安価な略式数珠(1,000円前後)でも十分です。
略式数珠と本式数珠の違い|宗派でどう変わる?
略式数珠(片手数珠)
一般的に販売されているのがこのタイプ。
珠の数が略され、どの宗派でも使える汎用型として人気です。
はじめて持つならこちらを選びましょう。
本式数珠(正式数珠)
宗派によって異なる仕様です。以下に代表的な例を紹介します。
- 浄土宗:二輪念珠。珠の数や構造が特徴的
- 浄土真宗本願寺派:左手で包むように持ち、数珠は手の中で見せない
- 曹洞宗・臨済宗:珠108個で構成された輪を左手にかける
- 日蓮宗:中房が二本、複雑な構成が特徴
本式数珠は宗派がわかっている方や、お寺の檀家に入っている方が対象です。
通夜・葬儀・法事での使い方マナー
正しい持ち方・出し方
- 焼香前:左手に数珠をかけ、合掌の際に数珠を手に添える
- 合掌時:数珠を中央で垂らすように手を合わせる
- 焼香後:念珠袋に入れ、バッグにしまう
避けたいNG行動
- 手首にぐるぐる巻く
- カバンの外に出しっぱなし
- 机の上に置く
法事・一周忌・初盆での数珠の使い方|通夜・葬儀との違いは?
数珠は通夜や葬儀だけでなく、四十九日法要・一周忌・三回忌・初盆など、仏式の法要全般で使用します。
いずれの場面でも、基本的な持ち方や扱い方のマナーは同じですが、法要の形式や場の雰囲気に合わせた配慮が求められます。
法事での数珠の使い方
法要の読経や焼香の際に、数珠を左手にかけ、合掌する際に軽く添えるのが基本です。
住職が読経している間も、数珠を手に持っておくと自然です。
式場では椅子に座ったままの焼香もあるため、数珠の取り扱いに注意しましょう。
一周忌・三回忌の場面
一周忌・三回忌など年忌法要では、親族が中心の私的な場になることが多く、格式ばった式典ではありませんが、略式数珠を持参するのが一般的なマナーです。
- 親族・友人が集まる仏前で焼香の際に使用
- 読経中は膝の上で軽く数珠を持つのが自然
- 終始手に持たなくてもよいが、丁寧に扱うことが大切
初盆(新盆)での使い方
初盆(新盆)は故人が亡くなって最初に迎えるお盆のことで、特別に盛大に営まれることが多い法要です。
地域や宗派によって異なりますが、住職による読経や焼香の時間がある場合は、数珠が必要になります。
- 白提灯・供花・香典とともに、数珠の持参が基本
- 家庭での法要でも、仏前で焼香があるなら数珠を使用
- 親族以外の訪問者であっても、略式数珠があると好印象
このように、数珠は法事や供養の場面でも常に必要とされる重要な仏具です。
通夜・葬儀だけではなく、年忌法要・お盆などの場でも繰り返し使う機会があるため、略式数珠を1本持っておくと非常に便利です。
数珠のお手入れ・保管方法
数珠は神聖な仏具ですので、丁寧な扱いを心がけましょう。
- 使ったあとは柔らかい布で汗やホコリを拭く
- 直射日光や高温多湿を避けて保管
- 念珠袋に入れて保管(バッグの底に直に入れない)
おすすめ数珠ブランド・価格帯・購入先
- Amazon・楽天:略式数珠 1,500〜5,000円。初心者向け豊富
- はせがわ・お仏壇の浜屋:品質重視の略式〜本式数珠(3,000〜20,000円)
- 京念珠 喜芳工房:職人仕立て・素材選びも豊富(10,000〜50,000円)
価格に関わらず、房の形状・素材・サイズ感が大切です。
通販でも「略式 数珠 女性用」などと絞り込めば安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 数珠を忘れてしまったらどうすれば?
A. 焼香や合掌は素手でも問題ありません。礼儀を守れば失礼にはあたりません。気になる場合は、葬儀社で貸し出してもらえることもあります。
Q. 数珠は1本あれば使いまわせる?
A. 略式数珠であれば宗派を問わず利用可能です。冠婚葬祭に対応できるよう1本持っておくのがおすすめです。
Q. 使わなくなった数珠はどう処分すればいい?
A. 不燃ごみとして捨てず、お寺や仏具店に相談し「お焚き上げ」や供養をお願いしましょう。
まとめ|数珠の正しい選び方とマナーを知って安心の弔問を
数珠は葬儀・通夜だけでなく、法要や初盆、一周忌などでも使用する場面が多い仏具です。
略式数珠を1本持っておくだけで、急な訃報にも冷静に対応できるのはもちろん、社会人としての信頼感にもつながります。
大人のたしなみとして、正しい数珠選びとマナーをぜひ身につけておきましょう。